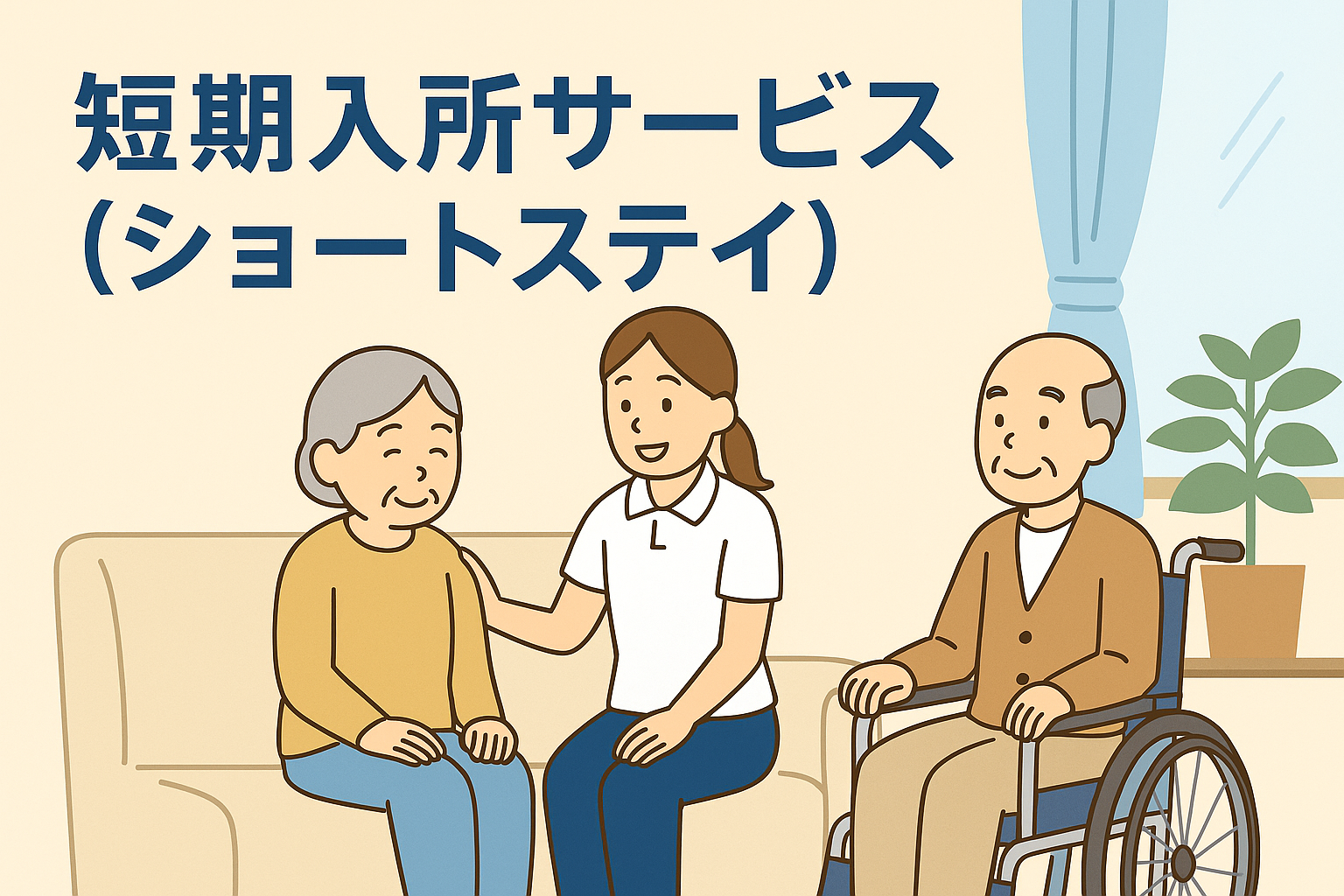認知症高齢者グループホームは、少人数の家庭的な環境で、認知症の方が自立した日常生活を続けられるよう支援する介護施設です。
正式名称は「認知症対応型共同生活介護」といい、介護保険の「地域密着型サービス」に位置づけられています。ここでは、施設の特徴や入居条件、提供されるサービス内容、利用料などについて解説します。

グループホームとは
グループホームは、認知症の診断を受けた高齢者が、介護スタッフの支援を受けながら少人数で共同生活を送る施設です。一般的な入居定員は1ユニットあたり9人以下とされており、家庭的な雰囲気の中で穏やかに暮らせるのが特徴です。
入居者同士で会話したり、一緒に食事を作ったりと、日常生活のなかで社会的つながりを保ちながら過ごします。こうした環境が、認知症の進行を穏やかにし、安心感を与えてくれるといわれています。
入居できる人の条件
グループホームには、次の条件を満たす方が入居できます。
- 要支援2または要介護1〜5の認定を受けている
- 医師により「認知症」と診断されている
- 施設と同じ市区町村に住民票がある(原則として)
- 集団生活を送るうえで他の入居者と協調できる
※「要支援1」の方は対象外となるため注意が必要です。
地域密着型サービスのため、原則として同一市町村の住民のみ入居可能です。ただし、地域によっては広域利用が認められる場合もあります。
施設の種類と運営形態
グループホームには、以下のような形態があります。
- 単独型:1つの建物全体がグループホームとして運営されるタイプ
- 併設型:特別養護老人ホームや小規模多機能型施設などに併設されているタイプ
- 共用型:他の事業所(例:小規模多機能)と共用スペースを使いながら運営されるタイプ
いずれも、家庭的な雰囲気を大切にし、職員配置は「3人の入居者に対して職員1人以上」が原則とされています。
サービス内容
グループホームで提供される主なサービスは、以下の通りです。
日常生活の援助
食事、入浴、排泄など、日常生活の介護を24時間体制で提供します。入居者ができることは本人のペースに合わせて自分で行い、できない部分をスタッフが手助けします。
調理や掃除などの共同作業
入居者がスタッフと一緒に家事を行うことで、生活リズムや社会的な役割を維持できるよう支援します。料理の手伝いや洗濯などを通じて、達成感や自己効力感を感じられるよう工夫されています。
機能訓練・レクリエーション
軽い体操、手作業、園芸、買い物など、楽しみながら行うリハビリを実施します。これにより、身体機能や認知機能の維持・向上を目指します。
医療との連携
施設内には常駐医師はいませんが、提携する医療機関と連携して定期的な健康管理を行います。体調不良時には往診や緊急搬送の体制も整備されています。
利用料金の目安
料金は施設ごとに異なりますが、介護保険の自己負担(1〜3割)に加えて、食費・家賃・光熱費などの実費がかかります。
例:要介護2・自己負担1割の場合(月額)
- 介護サービス費:約2.5万円〜3万円
- 家賃:約4万円〜6万円
- 食費:約3万円〜4万円
- 光熱費・日用品費など:約1万円
合計:約10万円〜14万円前後が目安です。
施設によっては入居時に「敷金」や「保証金」が必要な場合もあります。
メリットと注意点
メリット
- 少人数制で家庭的な雰囲気の中で暮らせる
- 一人ひとりの生活リズムを尊重した個別ケアが受けられる
- 認知症の進行を緩やかにする効果が期待できる
- 24時間スタッフが常駐しているため安心感がある
△ 注意点
- 医療的ケアが必要な場合は対応が難しい
- 市区町村ごとに入居制限がある(転居すると退去が必要な場合も)
- 定員が少なく、人気地域では入居待ちが多い
入居までの流れ
- ケアマネージャーや地域包括支援センターへ相談
- 施設見学・面談(本人の状態や希望を確認)
- 契約・入居前健康診断
- 入居開始(試験入居を行う場合もあり)
施設によっては、体験入居を受け付けている場合もあります。雰囲気やスタッフとの相性を確認してから正式入居を決めるのが安心です。
まとめ
認知症高齢者グループホームは、「暮らしの場」としての温かさを大切にしながら、専門的な介護を受けられる施設です。在宅介護が難しくなっても、家庭的な環境の中で穏やかに過ごしたい方に適しています。
入居を検討する際は、施設の雰囲気やスタッフの対応、医療連携体制などをよく確認しておくのがよいでしょう。
参考
- 厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1213」
- 厚生労働省『介護サービス情報公表システム』
- 各自治体介護サービスガイドライン(令和7年時点)