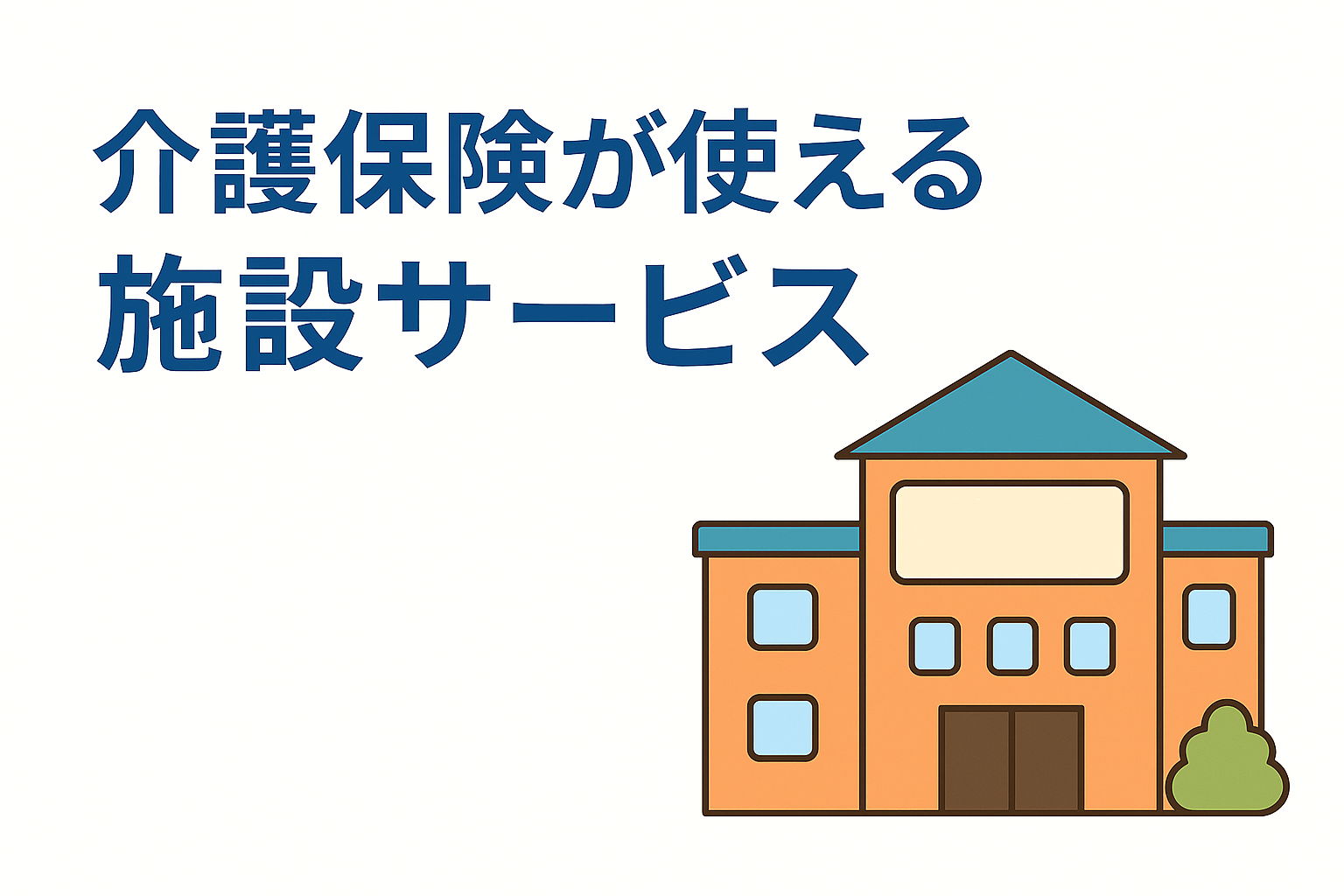介護保険制度では、必要に応じて福祉用具を購入できる仕組みが用意されています。これを特定福祉用具販売と呼びます。レンタル(福祉用具貸与)ではなく購入が認められているのは、衛生面の配慮が必要な用具や、使い続ける前提で自分専用とするのが望ましいものです。
対象者
- 要支援1・2、要介護1〜5の認定を受けている方
- ケアマネジャーがケアプランに位置づけた場合に利用できます
介護保険を利用して購入できるのは、原則として 年間10万円まで です。そのうち自己負担は所得区分に応じて1割〜3割となります。
購入できるもの
厚生労働省が定める「特定福祉用具」のみが対象です。代表的なものは次の5種類です。
- 腰掛便座
和式便器の上に置いて洋式化する便座や、ポータブルトイレなど - 入浴補助用具
入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽台、すのこ、入浴用介助ベルトなど - 簡易浴槽
空気や折り畳み式で設置できる浴槽 - 移動用リフトのつり具部分
スリングシートなど、利用者の体を支える部分 - 自動排泄処理装置の交換可能部分
レシーバーやチューブ、タンクなど衛生的に交換が必要な部品
これらは共用やレンタルに適さず、個人ごとに購入して使うことが合理的な用具とされています。
利用料(自己負担額)
購入費のうち、介護保険が適用されるのは年間10万円までです。
- 1割負担の方 → 上限1万円
- 2割負担の方 → 上限2万円
- 3割負担の方 → 上限3万円
例:8万円のポータブルトイレを購入した場合
- 1割負担 → 自己負担は8,000円
- 3割負担 → 自己負担は24,000円
購入費支給申請の書き方
特定福祉用具の購入には、市区町村への「購入費支給申請」が必要です。流れは以下のようになります。
- ケアマネジャーに相談
ケアプランに位置づけてもらうことが前提になります。 - 事業者で購入
指定を受けた福祉用具販売事業所で購入します。 - 領収書をもらう
購入後、領収書・カタログなどを保管しておきます。 - 市区町村に申請
「介護保険福祉用具購入費支給申請書」と必要書類(領収書、商品パンフレット、ケアマネジャーの意見書など)を提出します。 - 払い戻しを受ける
市区町村が審査し、認められれば自己負担分を除いた額が払い戻されます。
まとめ
特定福祉用具販売は、介護保険を利用して必要な福祉用具を購入できる制度です。レンタルでは不向きな便座や入浴補助用具など、個人専用で使うことが望ましいものが対象になっています。年間10万円を上限に介護保険の給付を受けられ、自己負担は1割から3割に抑えられます。
申請には領収書や商品カタログを添えて市区町村に手続きを行う必要がありますが、ケアマネジャーに相談しながら進めれば安心です。体の状態や生活環境に合わせて適切な用具を選ぶことで、自宅での生活をより安全なものにしていけるかと思います。